
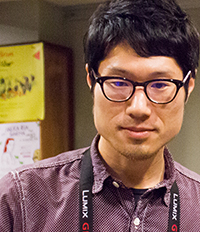
レポート 名古屋から
/酒井健宏(一般社団法人 名古屋シネマテーク、映像作家、映画鍋会員)
昨年の12月初旬、アーツカウンシル東京の助成プログラム「多様な映画観客育成プロジェクト/日本・インドネシア交流事業」(主催:ドキュメンタリー・ドリームセンター、NPO法人独立映画鍋、KOLEKTIF)に名古屋シネマテークから参加し、インドネシアに赴く機会を得た。ジョグジャカルタとジャカルタを訪問し、日本の映画を上映しながら現地の映画文化に触れるとともに、映画人や映画を学ぶ学生たちと交流を深めるのが目的だった。
日本から参加したのはNPO法人独立映画鍋の藤岡朝子さん、映画監督の深田晃司さん、NPO法人映画保存協会(FPS)の石原香絵さんと私の4名。到着後にはタイ国立フィルムアーカイブ副代表のチャリダー・ウアバムルンジットさんも合流した。そこから当プロジェクトのインドネシア側の主催である映画プロデューサーのメイスク・タウリシアさん、映画ライターのアドリアン・ジョナサンさん、ラインプロデューサーのサリ・モフタンさんによる手厚いサポートのもと、5日間にわたり映画祭や上映会場を巡り、貴重な出会いと経験を重ねることになった。
参加を決めるにあたり、私には多少の懸念がなかったわけではない。私の所属する映画館・名古屋シネマテークは地方都市のきわめて小規模なミニシアターである。自主上映団体を前身とし、常設館をオープンした1982年以来、今日にわたり独立系映画館として多様な作品の上映と紹介を積極的に引き受けている。老舗の名を戴くことのある一方、実際にはつねに映画を巡る激しい変化の波にさらされ、目の前の新しい状況に対処することで目一杯の日々が続いている。とりわけ近年、映画の配給・興行のデジタル化をはじめ諸々の事情から、国内各所の独立系映画館が閉館に追い込まれる事態が増える中、当館もその危機が目前にあると言える。こうした窮状をよそに、何か前向きな提言を述べるのは(可能であるにしても)空虚なことではないかという思いがあった。
また、私自身は名古屋市在住のしがない映像作家でもあり、愛知県内の大学や専門学校で学生たちが映像作品を作ったり理論を学ぶ際の講師を務めている。商業的な目的のみにとらわれない制作を推奨すると同時に、規模の大小を問わず多種多様な作品を受け入れながら楽しむ観客となるべきだと説いている。その信念に揺らぎはない。しかし、しばしば容易には超え難い壁を感じることがある。圧倒的な数の映画が、東京を介して、私たちの住む地域に届く。他方で、私たちの住む地域から「私の映画は(地元の、東京の、全国の)映画館で上映できないのか?」という質問があがると、答えに臆さざるをえない。いっそ不可能だと言うほうが前向きでいられるほど、それは簡単なことではない。
観客としての立場にも似た状況がある。「東京で大きな話題にならなかった映画を見るのはカネと時間の無駄ではないか?」という、ある種の真っ当な消費者感覚や、東京から発信される様々な情報に振り回されまいとする一種の防御反応が、鑑賞作品の選択や評価の一様化や保守化を招いている印象がある。多元的に生み出された映画たちが、一元的に発信されざるをえないという皮肉な状況に複雑な思いを抱きながら、届く一方の多様な映画たちを歓迎する単なる「いい人」であり続けることに、私自身は正直なところ気疲れを感じていた。
そんな手詰まりな状態にある中で訪問したのが今回のインドネシアだった。ところが、まず訪れたジョグジャカルタで、早くも私自身の狭量さに気づかされた。これは非常に幸いなことだった。ジョグジャカルタは、滞在中に私たちがよく京都を思い起こしたように、古都の雰囲気を漂わせる文化都市であると同時に、大学がたくさんある学生の街でもある。明るく活発な若い作家や上映者たちのやりとりには、首都ジャカルタに対する憧憬や羨望と、ときに引け目が混ざりあうことがあった。周縁から映画を求めることの自由と制約を味わいながら、学びの中で映画と関わる彼ら彼女らの姿勢に、私としては深い親近感と共感を感じることができたのだ。
ジョグジャカルタにはシネコンはあるが、いわゆるミニシアターは現在のところ存在しない。深田監督の『歓待』(2010)は「第9回ジョグジャ・ネットパック・アジア映画祭」のプログラムとして文化施設内のホールでの上映、松林要樹監督の『祭の馬』(2013)はジョグジャカルタのドキュメンタリー映画祭(FFD)のプログラムとしてホテルの多目的スペースに白い布を貼りパイプ椅子を並べての上映、土屋豊監督の『タリウム少女の毒殺日記』(2013)は学校(ジョグジャ・フィルム・アカデミー)の教室での上映だった。こうした即席の会場での上映は日本でもよくあることだ。ただし、特筆すべきはそこを訪れる観客たちの反応である。何時間とかかる遥か遠くから訪れる人もいれば、スケジュールの変更を寛大な態度で受け入れながら待つ人もいる。主催の皆さんの尽力があり、どの上映も多くの席が埋まった。そして上映が始まれば、会場の誰もが作品の内容に直接的な反応を返しながら最後まで積極的に鑑賞していた。さらに上映後に議論の機会が設けられると、テーマに沿ってじっくりと時間をかけて意見を述べあう光景が見られた。
議論される話題の中には、自主製作でドラマやドキュメンタリーを作ることの困難のみならず、配給や上映に伴う困難についても数多くの言葉が重ねられた。また、商業的に扱うことが難しい複雑なテーマを持つ多様な作品たちをどのように受容し、あるいは保護してゆくべきかを制作者、上映者、アーキビスト、観客の垣根を越えて話し合う展開も見られた。立ちあがる声に素朴さを感じることはなく、そこにはむしろ私自身が抱える悩みと同じものがたくさんあった。初めに私が考えたような、無理に前向きな装いなどまったく必要なかったのだ。
この印象はジャカルタに移動してからも変わらなかった。現在のところインドネシア唯一のミニシアターであるキネフォーラムを会場として、『歓待』と『タリウム少女の毒殺日記』の上映と、監督を交えての質疑応答が行われた。予定時間を大きく超えての議論に、学生を中心とする多くの人たちが参加した。キネフォーラムは規模も設備も名古屋シネマテークに非常に近く、毎日の興行は難しいものの、主に週末を活用しての特集上映やイベントを行っている。この日は必ずしも映画を専攻しているわけではない様々な大学の学生たちが集まり、それぞれの上映活動や創作活動について報告しあう機会もあり、互いに刺激を受けながら映画を媒介として接点を見いだそうしていた。
連日、定刻を過ぎてのスケジュール進行に、主催者側としては気を揉んだに違いない。それがインドネシアらしさの一つであることを、メイスクさんは私たちに繰り返しの謝罪とともに伝えてくれた。しかし、私にとっては滞在期間中を通して、まさにこの点に関して、確たる気づきが得られたと思っている。文化というものは、時間をかけて生まれるものなのだ。一見して無意味や無価値と思われる隙間にこそ文化が根をはる素地があり、制限を超えたところでの濃密なやりとりこそが文化の垣根を取り払ってゆく。多様な文化の共存について考えるのであれば、なおさらである。インドネシアはそもそも非常に多くの島々から構成され、一つの国とはいえ多民族、多宗教、多言語が当然のものとして並存している。数えきれないほどある「違う」の中から、時間をかけて「同じ」を見つけ出すことが、多様でありながら重なりをもつ文化を育んできたのだと思えてならない。
ジョグジャカルタでの上映後の質疑応答に登壇した藤岡さんが、たくさんの観客と一緒に大画面で映画を見ることの意義に関して「早送りや一時停止のできない映画館の暗闇は日常を離れることのできる神聖な場所の一つだ」と述べたように、スクリーンでの映画体験には個々人が時間を制御できない公共性と、それゆえの気高さが備わるものだ。インドネシアの映画人と観客たちには、興味関心を超えての親密な関係や、上映中に沸き起こる直接的な反応、上映後の濃密なやりとりなど、映画の気高い公共性を増幅させ展開しようという姿勢が数多く見られた。
ただし他方で、その気高い公共性は、私たちの時間を制御し、一つの方向へと駆り立てる手段として利用されやすいものであることもまた、映画史をひも解けばいくつも示すことができる。最終日にジャカルタで訪れたインドネシア国立映画製作所(略称PFN)は、現在は閉鎖され敷地の大部分が廃墟と化しているものの、プロパガンダ映画の制作をはじめ政府による映画統制政策の象徴的な意味合いを持つ施設だった。そして、私たちにとっても忘れてならないのは、この施設がもともと太平洋戦争中の日本軍政下で、日本人の技術者の指揮によって建設されたということである。施設の取り壊しと再開発の是非を巡り、ここでも映画人とジャーナリストが集い議論が交わされた。歴史的な遺産としての重要性とともに、表現の自由について考えることを忘れないための保存を訴える声に胸が熱くなった。
現在ここは、廃屋になった施設内に16mm映写機とスクリーンを設置して上映スペースとし、激しく劣化が進む残された映画フィルムたちをアーキビスト団体Lab Laba Labaが修復、保管する活動を行っている。その活動を見学し、石原さんとチャリダーさんを交えて日本やタイでのフィルムの収集と修復、そして保存の活動についても知ることができた。私にとっては、これまで映画について考える際にアーカイブの重要性に対する認識が抜け落ちがちだったことを反省するよい契機になった。同様の反省は、ジョグジャカルタでの小さなドキュメンタリー映画祭でも感じたことだ。地域の映画祭を通じて様々な自主映画の上映や収集を行い、カタログを作成し、さらなる閲覧や上映の機会に繋げようという発想は、たとえば私の住む名古屋市でも実行に移すことが可能だ。日の目を見ずに消えてゆく映画が身近にたくさんありながら、「東京から届くばかりだ」と嘆いていた身を恥ずかしく思った。
そして、インドネシアに保管されている小津安二郎監督の『東京物語』(1953)を現像当時のままインドネシア語字幕付きの16mmフィルムで鑑賞するという希少な体験をした後、いよいよ帰国の途に着くことになった。映画作家、上映者、観客のいずれの多様性についても、私にとっては何か有益な提言ができたかと言えば、自信がない。むしろ、インドネシアの映画人と観客の姿勢から学ぶことのほうが圧倒的に多かった。あらためて、日本の状況や私自身が住んでいる地域のことを考えずにはいられない。私たちは、時間をかけて多様な文化を生み出そうとしているだろうか。多様性に振り回されないために過度な一様化や保守化に走ってしまいがちである一方、本当は、多様性を当たり前のものとして受け入れながら、じわりじわりと「同じ」を見つけ出すことに、もっと価値を置いてもよいのではないか。そんなことを考えながら、今この報告を書いている。
報告の終わりとして、インドネシアと私の住む地域との関わりについても述べておきたい。愛知県は、都道府県別に見てインドネシア国籍の人々がもっとも多い県の一つだ。2014年の前半の統計でも約3000人、全国一位である。その多くは、自動車産業を筆頭にたくさんの工場がひしめくこの地域で働くためにきた人々であることは想像に難くない。いまだ受け入れたという実感を持たぬままの多様性が、実は私たちのすぐ身近にあることに気づく。彼、彼女らはどんなことを考えながら、ここで毎日を過ごしているのだろうか。顔を合わせ、話してみたいと思った。もしそれができるのであれば、さまざまな映画の上映を介して行いたい。なぜなら、多様な映画体験は、その気高い公共性ゆえに、私たちの共通理解を深めるためのより有効な手だてになるはずだからだ。
以上、所見を述べるにとどまったことに恐縮しつつ、今回の訪問を深い配慮とともに温かく迎えてくれたインドネシア・チームと支援者の皆さん、また旧知の仲であるようにすぐに打ち解けてくれた日本チームと支援者の皆さん、そして背中を押して送り出してくれた名古屋シネマテークのスタッフをはじめ多くの皆さんに心より感謝したい。本当にありがとうございました。
+++++++++++++++++++
酒井健宏
1977年、愛知県生まれ。名古屋市在住。名古屋大学大学院情報科学研究科博士後期課程中退。映像作家・映画研究。大学・専門学校にてパートタイム教員をしながら制作に携わる。98年に大学の映画サークルに所属したことがきっかけで制作を開始。07年『キッス占い』がTAMA NEW WAVEコンペティション部門に入選。11年『CSL/タカボンとミミミ』がうえだ城下町映画祭自主制作映画コンテストで審査員賞を受賞。
http://loadshow.jp/director/24
・全体概要
・総合報告(PDFファイル)
・主要なプロジェクトメンバー
・第一部 日本
・第二部 インドネシア
・「映画上映者の国際交流!インドネシア編」レポート/石原香絵(NPO法人映画保存協会)
・参加者の感想
–インドネシア滞在レポート/深田晃司
–映画上映者の国際交流!(インドネシア編)レポート・名古屋から/酒井健宏
–「映画上映者の国際交流!インドネシア編」に参加して /石原香絵
・日本編レポート(外部リンク)


