
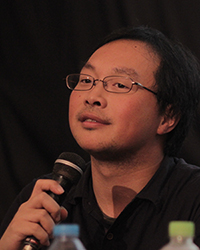
インドネシア滞在レポート
/深田晃司
2014年12月5日、ジャカルタ空港は冷房が壊れ蒸し風呂のようで、国内線への乗り継ぎを目指してせかせか歩く日本人一向の顔に汗が浮かびます。「あ」と私の前を歩いていた石原さんが声を挙げる、その視線の先には大きな荷物を抱えた女性がひとり。タイ国立フィルムアーカイブ副代表のチャリダー・ウアバムルンジットさんの姿がそこにありました。
「映画上映者の国際交流! 」と銘打たれた一連の企画は、11月にはインドネシアから映画プロデューサーでKOLEKTIF 代表 のメイスク・タウリシアさん、『Cinema Poetica』編集長のアドリアン・ジョナサンさん、映画祭企画者でラインプロデューサーのサリ・モフタンさんの3名を日本にお招きし、山形ドキュメンタリー映画祭の藤岡朝子さんのファシリテートで、大阪、神戸、名古屋、東京と日本の映画上映施設を中心に視察が行われました。そのアンサーソングのような形で、日本からインドネシアに映画関係者が派遣されることになりました。
同行者は、名古屋シネマテークの酒井健宏さん、映画保存協会代表の石原香絵さん、そして藤岡朝子さんの私を入れて4名です。映画を作る人、見せる人、保存する人、女性2名男性2名とバランスとしてはちょうど良いメンバー構成だったのではないかと思います。この日本人チームにタイから合流したのが、チャリダーさんでした。
12月5日から11日まで、基本的には全体行動で視察やシンポジウムが連日行われました(基本的には、というのは、私は滞在中に体調を崩し全行程には参加できなかったからです)。
私が主に関わったのは、拙作『歓待』の上映と、その後のシンポジウムへの参加でした。
■12月6日。大きいスクリーンで映画を見るということ
映画は2回上映されました。一回目は12月6日、ジョグジャカルタにて。ホテルを11時出発のはずが、みんなでなんとなくお茶をしているうちにあれよあれよと出発時間が延びてゆく、のんびりとしたインドネシア時間を楽しみつつ、午後2時に雨のそぼ降る文化施設「タマン ブダヤ ジョグジャカルタ(TBY)」 に到着。ジョグジャカルタでは今、第9回ジョグジャ・アジア・ネットパック映画祭が開催中で、その関連イベントの一環として『歓待』は上映されました。
会場は歴史を感じさせる公民館という印象で、開場前に慌ただしく映写チェックを済ませました。観客は印象としては若い人が多かった気がします。日本で開催されたシンポジウムで、メイスクさんがインドネシアのコミュニティに来るのは20代や学生とか若い人達がほとんどだと仰っていたのを思い出しました。
上映後はそのままの流れで、「Diversity and Big Screen Experience」 と題された討論会に移行しました。列席者は、映画祭プログラマーのイスマイル・バスベスさん 、アドリアンさん、メイスクさん、藤岡朝子さん、チャリダーさん、そして私の6名でした。
DVDやブルーレイが普及し、大型テレビも一般化、インターネットでも映画がダウンロードできるようになったこの時代に、映画館のスクリーンで映画を見ることの意義とは何か、意見交換がなされました。
いつしか外の雨脚は強さを増して、屋根を打つ雨音が会場の中にまで響きます。ちょうど私の目の前の机の上では天井から滴る雫が池を作り始めマイクを慌てて避難させたりしていましたが、そんな雨も会場の熱気を沈めるには至らず、多くの意見が登壇者と観客の間を飛び交います。
登壇者側の多くが、スクリーンで映画を体験する重要性を訴えました。「一時停止や早送りができない映画館の暗闇は、忙しい日常を離れて瞑想できる神聖な場所」と映画館を表現する者もいれば、「作り手の意図がもっとも正確に再現される場所が映画館の暗闇の中である」という意見も出ました。インドネシア側、日本側、それぞれから飛び出す意見に刺激を受けて、私もいくつか発言させて頂きました。当日語り切れなかったことも含め、この場を借りて少し述べさせて頂きます。
私は、スクリーンで映画を見ることと、家庭のテレビモニター(今であればスマートフォンなど)で映画を見ること、それぞれを絵画における美術館の鑑賞と画集での鑑賞に例えて話をしました。画集で見た絵に感動できるように、DVDで映画を見て心揺さぶれることもあると思います。大事なのは、どこで見るかということではなく、その人の人生にとってどのタイミングでどんな映画と出会えるか、だと私は考えています。
じゃあ、映画館はなくてもいいのか、というともちろんそうではありません。お客さんが足を運び易い環境さえ映画館側が準備できれば、テレビで映画を見て感動した人は映画館に自然と足を向けてくれるのではないか、と私は楽観的に構えています。なぜなら、地上波のゴールデンタイムにいわゆるアート系映画が上映され、ケーブルテレビやネット配信も盛んでありながら、映画館へのインフラを整えることで下降する観客動員数をV字回復させたフランスのような国もあるからです。
画集がどれだけ精緻に絵画を印刷できるようになっても、美術館に行く人は絶えません。大事なのは、いかにテレビ、ネット、映画館それぞれにちゃんと映画作品を供給し、時間軸と空間軸の両面において観客が気安く映画と触れられる多様な環境と機会を準備できるかではないでしょうか。
そして、映画を見る最高位の環境として映画館の立場を維持したいのであれば、やはり本気でスクリーンで映画を見せたいと願う映画人の存在が不可欠で、もし私達がその思いを失った瞬間、画集しか存在しない世界が当たり前のように訪れるのだと思います。しかし画集でみる絵画と本物の絵画はやはり別物であるように、例え複製芸術であれ映画もまた同様であることを、私達は根気強く説明し浸透させていかなくてはいけないのでしょう。
このシンポジウムで、インドネシア・タイ・日本の映画人それぞれのスクリーンへの熱い思いを目の当たりにし、まだしばらくは映画館文化は大丈夫だな、とそんなことを考えさせられるシンポジウムでした。
■12月9日。インドネシアの若い熱気
この日は移動日で、朝早くにホテルを発ちジョグジャカルタからジャカルタへのフライトでした。夕方から、2回目の『歓待』上映となりました。250人は入る前回の大きなホールとは打って変わり、45席で満席のミニシアター「キネフォーラム」が今回の会場です。この日、集まった観客の大半は、各地で映画上映団体を運営する若い学生達でした。
『歓待』上映後は簡単な質疑応答をし、その後は各団体の自己紹介タイムとなりました。それぞれの団体が独自色を持ち、上映だけではなく制作を行っていたりもします。日本で言えば映画サークルに近い雰囲気なのかも知れませんが、事前に日本でのシンポジウムで、検閲の厳しい中での自主上映団体の重要さというのをインドネシアの映画人たちから耳にしていたので、話を聞く方もつい熱が入りました。
しかしやはり印象的なのは、前回のジョグジャカルタでの集客を見てもそうでしたが、インドネシアにおけるその全体的な映画人口の若さでした。
これは、隣の芝生は青い的な贔屓目もあるのかも知れませんが、日本の映画に携わる若者がどこかしらに老成していてときにくたびれているようにさえ感じるのに比べ、インドネシアの彼ら彼女らはもっとシンプルに率直に映画と向き合っているように思えました。
恐らく、私がこう感じてしまうのは、ジョグジャカルタでの松林要樹監督『祭の馬』にたまたま観客として来ていて、上映後に話す機会を得たひとりの若い女性の記憶が強く残っていたからです。彼女はアニンダというジョグジャカルタで大学に通う20歳の学生で、映画が好きで、大学に通いながら自分の生まれた街で定期的に映画の上映会を企画・開催しているという。その真っ直ぐな瞳はこちらがたじろぐほど力強く、上映会を通じて彼女自身がいろいろなことを発見し成長していった様を生き生きと語るその姿は見ていて気持ちよいものでした。一方で食卓を囲みながら、日本の映画人たちに対して日本では自国の戦争責任についてどう教えているのかと問いかけるなど、映画の世界に自閉せず彼女なりの思想をしっかり持っていました。つい現代の日本の20歳と比べ溜め息が出てしまいますが、もちろん自分自身の20歳の頃を思い浮かべればいかにも頼りなく、彼女はずっとしっかりしていたと思います。
ちゃんと自分自身の考えを持ち他者とコミュニケーションを取る、という「社会人」としての基本的な能力が日本人は圧倒的に劣っている。これは、インドネシアに限らずヨーロッパでもどこでも、特に多くの国の若者と話していて感じることです。
映画で何かを表現する、映画を見て何かを感じて、その感じたことを人に伝える、というのは特殊な能力ではなく、つまるところその人本人の個性や人間としての深みこそが重要になります。
この5日間の滞在を通じて感じた、インドネシア映画人の「若さ」は、老衰しつつある日本の映画業界、引いては日本という国そのものに取ってまさに抽出すべき美徳であるように感じました。
日本の若い映画人に、もっと海外の同年代の映画人と触れ合う機会を作るべきだ。そう実感できる貴重な機会となりました。
以上、駆け足にはなりましたが、5日間のインドネシア滞在を通じて感じた雑感を認めさせて頂きました。貴重な機会を頂けたことを感謝致します。
++++++++++++++
深田晃司
1980年生まれ。大学在学中に映画美学校3期フィクション科に入学。2001年初めての自主制作映画『椅子』を監督、2004年アップリンクファクトリーにて公開される。その後2本の自主制作を経て、2006年『ざくろ屋敷』を発表。パリKINOTAYO映画祭にて新人賞受賞。2008年長編『東京人間喜劇』を発表。同作はローマ国際映画祭、パリシネマ国際映画祭に選出、シネドライヴ2010大賞受賞。2010年『歓待』で東京国際映画祭「ある視点」部門作品賞受賞。2013年には『ほとりの朔子』がナント三大陸映画祭、フリブール映画祭等で受賞。三重県いなべ市にて地域発信映画『いなべ』を監督。その後『さようなら』等、製作中。2005年より現代口語演劇を掲げる劇団青年団の演出部に所属しながら、映画制作を継続している。
・全体概要
・総合報告(PDFファイル)
・主要なプロジェクトメンバー
・第一部 日本
・第二部 インドネシア
・「映画上映者の国際交流!インドネシア編」レポート/石原香絵(NPO法人映画保存協会)
・参加者の感想
–インドネシア滞在レポート/深田晃司
–映画上映者の国際交流!(インドネシア編)レポート・名古屋から/酒井健宏
–「映画上映者の国際交流!インドネシア編」に参加して /石原香絵
・日本編レポート(外部リンク)


